未来医療開発部
大阪大学医学部附属病院に設置された未来医療開発部は、大阪大学の研究機関をはじめとするアカデミアの優れた発見・発明を医薬品・医療機器・再生医療製品等として実用化するための一連の研究開発プロセスをシームレスに支援する未来医療センターと、治験、観察研究を含む自主臨床研究の支援を行う臨床研究センター、介入臨床試験や分析研究のデータマネジメント、統計解析を独立して総合的に支援するデータセンター、高まる「グローバルヘルス」のニーズに対応した外国人患者や世界各国からの医療従事者の研修の受入れや日本発の革新的医薬品・医療機器の海外展開を支援する国際医療センター及び各センターの機能を横串に助ける部長直轄の組織支援室から構成されます。これらのセンターが有機的に連携して、特定機能病院の責務である「高度な医療技術の研究・開発」を統合的・効果的に支援しています。
また、日本発の革新的な医薬品や医療機器の開発に必要となる質の高い臨床研究や治験を推進するための中心的役割を担う病院として医療法上に位置づけられたもので、厳しい要件を満たした医療機関のみが厚生労働大臣の認可を受けて指定される臨床研究中核病院として、本院は平成27年8月に指定されました。
大学などのアカデミアや医薬品・医療機器の企業の高度な研究が生み出す未来の医療技術を確実に実用化に結びつけることによって、難病の克服やわが国の喫緊の課題である高齢化社会への対策などを促し、国民の健康とともに「グローバルヘルス」に貢献できるよう、医療イノベーションを動かす原動力となって、医学・医療の未来を創造していくことを目指しています。
ご挨拶
未来医療の技術と人を創り育む
令和6年4月1日から未来医療開発部・部長を拝命しました宮川です。大阪大学ではアカデミア発の未来医療の開発を推進するため、2002年に全国に先駆けて附属病院に未来医療センターを設立しました。以降、本センターは歴代のセンター長(松澤元大阪大学医学部附属病院病院長、金倉現住友病院病院長、澤元大阪大学医学系研究科科長/医学部部長)並びに西田、坂田、江口前未来医療開発部長のリーダーシップにより発展し、我が国のトランスレーショナルリサーチ(TR)の拠点の一つとしての大きな役割を果たしてきました。
2007年からは、文部科学省橋渡し研究プログラム、厚生労働省早期・探索的臨床試験拠点整備事業の支援を受け、ARO(Academic Research Organization)としての体制を整備してきました。 さらに、2012年には未来医療センターを改組拡大して、未来医療開発部の新設を行い、2017年度にアカデミアの医療技術シーズの実用化のための橋渡し研究や、新規医薬品や医療機器の臨床試験を通じた実用化を一元的にサポートする「未来医療センター」、研究対象者の保護を最優先に、臨床研究の円滑な実施を支援する「臨床研究センター」、介入臨床試験や分析研究をデータマネジメント、統計解析を独立して総合的に支援する「データセンター」、医療の国際化に対応し「全地球的な健康」を促進するための、「国際医療センター」の4部門体制(4センター)となり、各センターが有機的に連携することにより、特定機能病院の責務である「高度な医療技術の研究・開発」を総合的・効率的に支援を行っています。
大阪大学医学部構成員は元来、イノベーションスピリットを持っており、創薬・再生医療・医療機器など幅広い分野にわたって、独創的な応用研究が進められてきた実績があります。
また、大阪大学内のシーズのみならず、大阪大学の特長である再生医療、細胞治療、遺伝子治療等を中心とする全国の優れたシーズの実用化、産業化に寄与するために、ACT west(Alliance for clinical translation, West Japan)を組織し、最近ではACT japan(Alliance for clinical translation of Japan)に発展させてきました。このような長年の戦略的な体制整備の結果、現在では、支援している臨床研究や医師主導治験の数は我が国でのトップレベルとなっています。
今後の喫緊の課題は、本ARO組織をサステナブルにしていくことであり、そのために、シーズの社会実装、すなわち、産業界への導出や国際展開を加速していくことが必要と考えています。また、時代が変遷するに伴い、新しい医療ニーズがでてきますので、未来医療開発部もそれに対応していかねばなりません。今後到来する超高齢化社会においてはQOLに資する医療がますます重要になります。 換言すると、これまでの医療は、主として、病気が発症した後に介入して、臓器の機能喪失まで進行するのを食いとめることに主眼が置かれていました。健康な未来社会の実現のためには、病気が発病する前の未発病状態に対する介入も重要となります。 そのための鍵は、ゲノム情報の医療への活用だと考えます。今後、ICT技術を基盤として、ゲノム情報や医療情報といったビッグデータを臨床研究に応用する体制を整備していくことにも取り組んでいきたいと考えています。またこのような社会においてより医学以外の広範囲にわたる学問の力を結集することが必要と考えております。
COVID-19パンデミックにより社会は様々な課題を急速に抱え始めました。しかし、これを科学の力にて克服する努力が必要です。臨床研究は人を対象とする研究であり、社会の十分な理解を得ながら進めていくことが極めて重要です。この基本精神を大切にしながら、未来医療開発部全員の力の結集により、真に社会に貢献する未来医療の創成を目指します。何卒よろしくお願い申し上げます。

沿 革
| 2022年 |
|
|---|---|
| 2021年 |
|
| 2017年 |
|
| 2015年 |
|
| 2014年 |
|
| 2013年 |
|
| 2012年 |
|
| 2011年 |
|
| 2010年 |
|
| 2009年 |
|
| 2007年 |
|
| 2005年 |
|
| 2004年 |
|
| 2003年 |
|
| 2002年 |
|
理 念
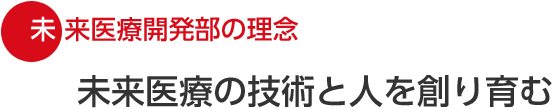
行動指針
- 医療技術の開発、評価に必要な情報、技術、支援を提供し、研究者とともに高度な医療技術を育て、研究成果を社会に還元する
- 橋渡し研究、臨床研究の推進を通じて医療技術の向上、研究者の育成、医療産業の発展に貢献する
- 患者、被験者の健康、権利の保護に万全に配慮する
- 先進性・創造性を意識し、自ら考え、進んで行動し、常に前進する
- 道徳観に根ざして、思いやりのある、社会から信頼される集団となる
- コミュニケーションを大切にして、協調性のある職場環境をつくる
組織図※2025年4月改組
